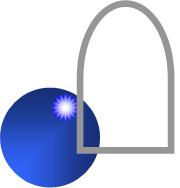|
|
そこにいるのは彼一人だった。何十、何百万年もの間、そこからこの惑星ガンダルフを見守ってきたのだ。 彼が属していた人々は何千億光年も遠く離れた、何処か知れない宇宙へ去って行った。当初は連絡があったものの、すでに数百万年も前に音信は途絶えている。それでも彼は一人、ここから惑星ガンダルフを見守ってきた。 |
|
|
長い、長い間、天空の間の大きな窓から下の惑星ガンダルフを見守り続けた彼は、いつしかガンダルフの守護者と呼ばれるようになっていた。彼の住むのは天空の城、オリンエルブだった。ガンダルフに住む住人達は、ガンダルフの守護者をガウェン・レヴンと呼んだ。 かつて、ガンダルフでは非常に進んだ文明が存在した。その彼らが、天空の城を作り、去っていった者達であり、彼の属した人々だった。しかし、今現在ガンダルフに住んでいるのは、宇宙のことなど何も知らない人々だった。彼らは、ガンダルフを去った人々の末裔でもあるのだが、文明は格段に落ちていた。 |
|
|
|
もともとガンダルフの人々は、呪文を使った文明を築いていた。呪文によって様々なエネルギーを変化させ、それによって、形を作ったり壊したり、また、移動したりしたものだった。そのためにはかなり複雑な呪文もあり、エネルギーを取得する高度な呪文も存在した。そのすべては、天空の城に残してある。 だが、今のガンダルフの住人は、呪文の使える人々と、使えない人々に分かれ、仲たがいをしていた。呪文の使えるものを、魔物と呼び、使えないものはただの人間と呼ばれた。呪文も様々に変化し、太古の人々が使っていたものとは違うものとなっていた。 |
|
|
魔物と人間との違いは、それだけではなかった。彼に言わせれば、魔物とは本来のガンダルフに住んでいた人々に一番近いものであり、人間とは、ガンダルフの人々が宇宙に出て様々な星の人々と交わった結果、気質や形状が多少変形したものであった。だが、彼らはそうしたそもそもの自分たちの歴史すら忘れてしまい、いまや人間と呼ばれるものがガンダルフでは多勢を占め、魔物と呼ばれるものが少数に追いやられていた。その結果、魔物たちは本来あるべき姿を知らず、まさに無法の人間さながらの生活をし、人間はそうした魔物を委棄し、唾棄すべきものとしている。 |
|
|
|
この状況は彼にとっては、耐え難いものだった。本来のガンダルフを知る彼は、決して魔物とか人間とかいう思いはなかった。その願いは、ガンダルフにおいてかつての文明と栄華を再び取り戻したいと考えており、それがガンダルフの人々の幸福に繋がると思っているからだった。 天空の城オリンエルブの天空の間の中央にある巨大な球状の装置は、長い間使用されなかった。それはここを去った人々が連絡を取るためにおいていったものである。かなり遠くの銀河まで交信が可能な装置だった。その装置は使われると明るい光を増す。そして、それを見守る彼の心に、通信が入ってくるのだ。遥か彼方に去った人々が時間と空間を超越して、このオリンエルブと連絡をとるときにのみ使われたもの。それが、今急に光を増していた。 |
|
|
彼は、窓から視線を転じて、それを見た。 信じられぬ思いで見つめる彼の心の中に一筋の光が入ってくるのが感じられた。その光は、彼の心の中で言葉となった。 『……遥か彼方より、人々がやってくる。このガンダルフを目指して。彼らは、この星に住まうことを望んでいる。我ウルは、彼らを迎えて共に、歩んでいくことを願うものなり……』 はじめそれは、かつての仲間からの通信とも思われた。だが次の瞬間、それとは違うということに気づいた。その言葉は「我々」ではなく、「我ウル」とある。それは何百万年も音沙汰のなかった、彼の属していた人々が信じていた神ではなかったか? |
|
|
|
かつて、ガンダルフの人々が宇宙へと発展していった頃、その神の名は多くの人々が知っていた。その頃は、その神の姿を見たり、啓示を受けることのできる者も存在した。ただし、その者たちは装置を使って啓示を受けたのではない。神の啓示を受けるという特殊な能力を持った者のみができたのだ。彼にはその神を見たり啓示を受けたりすることはできなかったが、その神を信じ、今までこの城で暮らしてきたのだ。 今のガンダルフの人々もその神の名を知っている。その神の名も一つではない。噂では、かつてのように、その姿を見たり、啓示を受けたりすることのできる者もいるようだった。だが、その神はかつてのように、人々に宇宙へ行くことを勧めたりはしなかった。おかしなことに彼すら、人々には神の一人として考えられている。 |
|
|
彼は何百万年もの間、天空の城で暮らし、ガンダルフの人々から神のごとく思われていた。しかし彼自身は自分を「神」であるなどと、おこがましくも思ったことはない。彼の属していた文明では「神」は確かに存在すると信じられていた。彼もそれを信じていたが、実際にそれを見たり感じたりすることは、彼自身にはなかった。今までは……。 これは初めての通信だった。これが本当に、『ウル』と名乗る彼の信ずる神からの通信であるなら。だが、今まで通信機で神との交信が可能だなどということは、彼自身も太古の人々でさえも考えなかった。人間の作った星間通信機で神との交信が可能だとは! |
|
|
|
彼は暗くなった通信機を見つめて、少なくともこのガンダルフに何か変化が起きようとしていることを感じていた。それが、良きものであってくれればよいのだが。 足元まで届く長い金色の髪を手で後ろに梳くと、彼ガルダ・ジロン・ルドは、ローブの裾を返して天空の間を去って行った。やがて来る人々を迎えるために。 |
|
|
天空の城は、惑星ガンダルフの衛星軌道上にあり、それ自身ガンダルフの周囲を自転していた。地上からは青い空に白く輝く点にしか見えなかったが、複雑な幾何学模様のような形をした天空の城は、ガンダルフの守護者の住まう場所として人々にはふさわしく見えた。 天空の城の近くに小さな光が明滅した。次の瞬間小さな宇宙船のようなものが現れ、城の周りを回った。 「あそこが、ガンダルフの番人の住処なの?」 小さな少女に見える人影が呟いた。船の大きなスクリーンに映る天空の城は、まるでオモチャの城のような無規則な形に見えたのだ。 |
|
|
「番人?守護者と言っていたがな。」 大人の男性に見える人影が、異を唱えて呟いた。 「どちらでも同じこと。ともかく着陸の許可を確認…?」 船長が指示をしていると、突然前面にあるスクリーンが明るくなり、人の姿が映った。 長い金髪を伸ばし、長いローブを着た姿の男は、最初は顔だけだったが、そのうち身体全体が映り、 「お前たちはどこからきた?」 と言うと、そのスクリーンから直接抜け出してきた。 船長はまだ言葉がわからないので、相手にはわからない言葉を喚くと、小さな少女に目を向けて促した。 「あなたは、誰?」 |
|
|
|
ガンダルフの守護者を怖がる気配も見せず、少女は尋ねた。相手が何も言わないと、重ねて言った。それは、ガンダルフの守護者である彼の属していた人々が話していた言葉だった。 「まず自分から名乗りなさい。ここは我々の船なのだから。」 その凛とした態度に、彼は少女に言った。 「私は、このガンダルフの守護者、ガルダ・ジロン・ルド。お前たちは、どこから来た何者だ?」 |
|
|
少女は彼を真正面からしばらく見つめると、静かに話し始めた。 「私達は、遠い銀河からやってきました。グリトスという星に住んでいたのですが、その星がこれから災厄に見まわれ、住めなくなるので、移住する惑星を探してやってきたのです。確か、この星を指導している神、『ウル』という名の神から、通信を受けました。ここにガンダルフという惑星があるということを聞いたのです。この星なら私達を受け入れてくれるということでしたが、あなたはその話を知っていますか?」 「何者かがやってくる、という知らせは聞いた。だが、詳しくは、聞けなかった。お前たちはグリトスという星に住んでいたということだな。」 |
|
|
|
「そうです。私はその星の女王アスカの末の娘、リーラといいます。こちらは伯父のヨシミツ。そして、この船の船長、ゴスンク。あなた方が私達を受け入れる準備が整っているかを聞くために、他の者たちよりも先にここへ来たのです。」 リーラという娘の目は鋭かった。まるで、彼の思いを見抜いているかのように、感じられる。彼は、戸惑っていた。かつての宇宙へと発展していった太古の時代に、こうしたことが起きたならば、対応をすぐに整えられたに違いない。だが、肝心の惑星ガンダルフには宇宙のことなど何も知らない人々が住んでいる。彼らにこのことを、どう理解させたらよいのだろうか。 |
|
|
「ともかく、船をどこかに置きたいのですが、ガンダルフの守護者殿。」 船長が困り果てたように言った。すでに船は長い航路で疲労している。乗組員にも休みが必要だった。 船は天空の城の広場に降ろされた。 |
|
|
|
|
|
リーラとヨシミツは彼の後をついて船を出、天空の間に入った。そして、その中央にある球状の装置を見た。 「これは、かつて使われていた通信装置だ。ここに先ほど知らせが入った。だが、遠くから多くの人々がやってくるということのほかは、詳しくは語られなかった。」 「遠くの銀河とも交信できるものなの?」 「かつてはそうしていた。」 「ならば、高い次元の領域の波長を使っているのではないかしら。距離と時間を越えるにはそれに比例して高い次元の波長を使う必要があるから。それならば、あなた方が『神』と呼んでいた存在との交信も可能なはず。」 |
|
|
「だが、我々にはこの装置を使って『神』と交信できるなどと考えたものはなかった。」 「そうね。だからできなかった、というだけのこと。しようと思えば可能だったはず。」 「おまえは、どういう存在だ?どんなことを知っている。この装置をどこかで見たことがあるのか?」 娘の言うことは、見掛けとはかなりかけ離れていた。幼い年頃に見えるが、長い年月を生きてきた存在のような口の聞き方だった。一瞬遠くを見るような目をして、 「見たことがあるかもしれないわ。どこかでね。私はあまり一つ所に長くいたことはなかったから。旅をしていたの。」 「旅?宇宙船で?」 「少し違うけれど。似たようなもの。」 |
|
|
|
「では、おまえはそこにいる、伯父だという人間とは違う種族なのか。」 「いいえ、同じよ。」 「だが、その男は特殊な能力など持っているようには思えない。今のガンダルフの人間と同じではないのか。」 「伯父はグリトスの平均的な人間なの。グリトスの人間には特殊な能力をもったものはほとんどいない。たまにいるけれども。あなたの考えている、いえ、持っているような力とは違うものだわ。」 |
|
|
「おまえの母という人間は、やはり普通の人間か?」 「違うわ。母はアロミアの種族の血を引いているから、強力なテレパスでもある。アロミアは向こうの銀河では多くの惑星系を指導している、非常に高い文明を持った種族でね、テレパシーや、テレキネシスなどの特殊な能力を持っている。それは、あなたの持っている力とは基本的には同じだけれど、発動の仕方や方法が少し違う。」 「では、おまえはその母の血を引いているというわけか。」 「少し違うわ。私は実の娘ではないから。グリトスの人間として生まれたけれど、本来は違う。だから、彼らとは違う力を持っている。あなたとも違う力よ。」 |
|
|
|
彼にはリーラの話は正確には分からなかったが、ある程度理解できた。 「では、ここにやってくる者達は、いろいろな種族の寄せ集めなのか。」 「少しは混じっているけれど。ほとんどはグリトスの人々よ。そうね、だいたい二十億人になるかしら。」 「ちょっとまて、何人だと?」 「二十億人。」 「……!それは初耳だ。それほどの人数とは思わなかった。」 |
|
|
現在ガンダルフの人口は、十億に満たない。それでは、移住してくる人々のほうが多いことになる。その上、文明的にも移住者の方が高いように思えた。そうなってくると、本来のガンダルフの人々がすみに追いやられてしまう可能性が大きい。このまま彼らの移住を認めていいのだろうか。 ふいに黙ってしまった彼を、伯父のヨシミツは不安そうに見た。 「断りたくなったんじゃないか。」 「そうかもしれないわ。」 「おいおい、やっと見つけた移住先だろう。」 と、ヨシミツはあわてて言った。移住先を見つけるのにどれほどの時間がかかり、どれほどの苦労があったのか、ヨシミツはある程度知っていたのだ。 |
|
|
|
「でも、彼らの意見や意志があるでしょう。上の方で意見が一致しても、こちらの世界で納得しないのならば、どうしようもない。こちらの世界を取り仕切っているのは、彼なのだから。彼が断ることに決めたなら、仕方がないわね。」 ここで、ごり押しをして何になるだろうか。まさか、艦隊を率いて、この星を征服するわけにはいかない。そんなことをするには、第一遠すぎる。これから二十億という人々を運ぶためには多くの船と物資が必要である。戦いなどを引き起こしたら、物資も人命もその多くを犠牲にしなければならなくなる。そんなことになったら、元も子もない。摩擦を起こさずにできるだけ穏便にしたい、というのがアロミアや女王アスカをはじめとするグリトスの指導者の考えだった。移住先の人々と融和して、新しい文明を作るというのが目的なのだ。 |
|
|
彼は窓に近づき、そこに映るガンダルフを思案げに眺めた。いったいこれをどう判断すればよいのだろうか。断れば、彼らはどうするのだろうか。 この長い年月、ガンダルフを守ってきた彼は、他の恒星系で起きたことを知らないわけではない。宇宙航行技術を持った異星人同士が遭遇したとき、様々なことが起きる。その種族の性格にもよるが、一方がもう一方を征服するなど、よくあることだった。たいてい、より高い文明を持ったほうが支配勢力となる。今までガンダルフがそうした目にあわなかったのは、太古の人々が残した天空の城とそこに彼がいたからだった。 |
|
|
|
だが、それによって、まわりの他の種族よりもかえって文明度が低い状態におかれているような気がする。この銀河でも、多くの惑星で宇宙航行の技術が発見され、船がそれぞれの母星を中心に動いている。しかし、このガンダルフでは太古の人々が去って以来、そうした技術を発見する段階まで進んでいない。相も変わらず、呪文を使う文明ではあるが、それはこの惑星内にとどまっているのだ。その上、ガンダルフの人々の間でさえ、人間と魔物と色分けして一方を排除する考えは根強く残っている。 彼にはどうすれば、それをやめさせることができるのかさえわからない。いつもこの窓から、地上を見守っているだけなのだ。自分の無力さを痛感しているだけに、新しい移住者の到来は、絶好のチャンスになるかもしれないのだ。 |
|
|
リーラとヨシミツは彼がゆっくりと二人のところへ戻ってくるのを見守った。 「もし、この話を断ったら、どうするつもりだ?」 「他を当たることになるわね。たとえ、時間がかかっても。」 少女が嘘を言っているようには見えなかった。 「返事をするのは、もう少し待ってもらえないか。簡単には答えられない問題だ。お前達がどんな種族なのかも、私には皆目検討がつかないのだから。」 リーラとヨシミツは顔を見合わせた。困ったことだが、相手の言うことも分かる。 「どのくらいの時間がいるのかしら。」 と言いながら、リーラはあまり時間がかかるのではこちらが困るという表情をあらわに見せた。 「できれば、ガンダルフの時間でひと月の時間ぐらいだ。」 「わかりました。そのくらいなら待ちましょう。」 |
|
|
|
天空の間の中央にある球体の装置は、あれから変化はなかった。 彼は悩んでいた。突然やってきた彼らをガンダルフに受け入れるかどうか。総勢二十億人からなるという移住者の受け入れは、すぐには決断できなかった。相談しようにも、この天空の城、いやガンダルフに残っている仲間は一人もいない。彼らは何百万年もの昔、この星を去って、とっくに音信が絶えている。唯一、移住者がやってくるという情報をもたらしたのは、この装置から初めて下った啓示である。 その啓示がどこから来たのか、彼には分からなかった。だが、それがまんざらいたずらとも嘘とも思えないのは、そのあと彼ら、グリトス人の使者がやってきたからである。 そのうちの一人が言うことには、この装置を使って啓示が降りたのは、不思議でも何でもないというのだ。 |
|
|
だが、彼らがこの装置を使って彼を欺いた可能性が否定できない。もしかしたら、彼らグリトス人は太古のガンダルフ人よりも科学技術において優れているかもしれない。それで、この装置を使えたとしたら、『神』を偽装したのは彼らということになる。 考えればきりがない。 あとひと月だった。それが考える時間である。 彼は、窓からいつものようにガンダルフを見た。久しぶりに地上に降りてみようかと、ふと思った。 |
|
![]()
|
|
ガンダルフは工業化以前の文明で、まだ森も緑も汚れてはいない。 農民は人力で畑を耕し、道には馬と呼ばれる四足の動物が荷物を運んでいる。ここ、タントスの地では、ゆるやかな合議制の集落が作られ、国として統一された地域ではない。人口は少ないが、それに見合った農産物しかできないので、それ以上増えることはない。だが、余裕がないので、学問だけをするとか、社会を進歩させる知識の積み重ねをすることは難しい。それがまた、社会の進歩を妨げ、人口を抑制している。 そうであっても、住んでいる人間にとっては、それほどつらい社会ではない。 |
|
|
ただ、問題はあった。 魔物の存在である。 彼らは、人間社会からはみ出し、人間を規制している様々なモラルから外れて、あるいは生涯それを知ることなく、生活している。姿形も、人間とは少し違う。中には人間そっくりの魔物もいるが、一番違うのは、特殊な力を持っているということだ。それは、元来住んでいたガンダルフの人々の末裔であるためでもあった。 人間と魔物、というように別れて住むようになったのは、いつのことからだろうか。彼は、タントスにある湖の傍にたたずんで思い出そうとしていた。 |
|
|
|
太古のガンダルフの人々は宇宙船に乗るのではなく、少しずつのグループに分かれて、集団で呪文を使って次元を超えて移動して行った。移動先の惑星では、まず自分達の住む場所を確保し、様々なことを調べ、そこでその惑星に同化することによって、その惑星に住み着くものもあった。 その頃は、住み着いた惑星から帰ってくるものもあり、そうした場合、多少形質が変わっていることがあったのだ。そのため、元来のガンダルフの人々とは違った形質のものが混じるようになったのだ。 |
|
|
ただ、形質が変わるとなぜか呪文を使う力が減っていき、ガンダルフとの行き来が次第にできなくなっていった。そうして、音信の途絶える人々が増えていった。それでもガンダルフの人々が宇宙へいくという情熱がなくなることはなかったが、他の惑星に住み着くものはなくなっていった。ただ、様々な惑星を知りたいという目的でより遠くへ出かけるようになった。 なぜ、それほどガンダルフの人々が他の惑星へ行きたがったのか?それは自分達と同じような種族を見つけたかったからかもしれない。 まだその頃には、呪文を使う種族はほとんど見つからなかったし、この銀河では宇宙航行の技術をもった種族は他に二つを数えるのみだったのだ。彼らはガンダルフの人々とは違い、呪文を使わず宇宙船を使っていたが、不思議なことにこの二つの種族は仲が悪く、ガンダルフの人々が近寄りたいと思うような人々ではなかった。 |
|
|
|
彼は湖面を小波が漂うのを見つめていた。 その小波がだんだん大きくなり、人型になった。 「ここで、何をしている。ガンダルフの守護者よ。」 それは、今はガンダルフの住人である人間が湖の魔物と呼んでいるものだった。長い銀髪が水に濡れて光っている。湖の魔物は時折、この湖の傍にガンダルフの守護者がやってくるのを知っていたのだ。 彼はその魔物が水の惑星に太古の人々が訪れたときに、身体を変化させたために生じた形質を持っていることを知っていた。魔物でさえ、純粋なガンダルフの形質を持つものは少ない。 |
|
|
「ここは、いつも変わらない。おまえは、退屈はしないのか。」 「おかしなことを言われるものだな。退屈などしてはおらぬ。私は、この湖に満足しているここは静かで、穏やかだ。私の愛する者たちもいる。なぜ退屈するのだ?」 「人間は嫌いか。」 「嫌いだ。やつらは我らを嫌っている。特にあの神殿の者達は、私の子供達を退治するなどとぬかしている。そんな連中を好きにはなれぬのが、あたりまえであろう。」 彼はため息をついて、 「確かに。」 と頷いた。 |
|
|
|
「そういえば、マルトのはずれの森に、黒い魔物がいると聞いたが、知っているか?」 と、彼は尋ねた。 「ふん。聞いたことはある。その辺の魔物を束ねているとか。血なまぐさい連中だと聞いている。」 その言葉には同じ魔物であるのに、好意を持っていないことが伺われた。 「おまえは、その魔物を嫌っているのか?」 「魔物など嫌いだ。あの連中は私の子供達を食らおうとしたのだ。」 「よほど、腹をすかせていたのだろう。」 |
|
|
人間と同じ事をすることが嫌いな彼ら魔物は、人間のように畑を作ったりはしない。自然の木の実を取ったり、魚を取ったりするが、中には人間や他の魔物を襲ってそのエネルギーを食用にしている者さえある。 「腹をすかせていたとして、なぜ私の子供達をねらうのだ。他にいくらでもエサにするものはあるだろうに。」 「エサ?人間をエサにするというのか?」 「ふん。魔物だからと言って、人間をエサにする必要はないではないか。森には人間でも食べられる木の実などがたくさんあろうほどに。なぜ、人間を食らう必要がある。まして私の子供達を。」 |
|
|
|
湖の魔物は他の魔物と少し考えが違うようだ。他の魔物なら、人間を食らうのを当たり前のように言う。 「おまえは、人間を食らったりしないのか?」 「ふん。私はそんなもの必要ないからね。湖にはたくさんエサになるものがある。なぜ人間を食らう必要がある。私が人間を食らうなどというのは、あの神殿の連中、神の僕などと自称している連中が勝手に言っていることだ。」 彼は、初めてみるような目で湖の魔物を見た。この魔物との付き合いは、他の人間と比べたらかなり長い。もう数千年になる。だが、こんな話をするのは初めてなのだ。 「あの、神殿の連中の傍若無人な様はまるで自分達だけが、神に選ばれていると思っているようだ。」 「魔物は、神を好かないというが、おまえは『神』をどういうものだと思っているのか?」 |
|
|
湖の魔物は眩しそうに太陽を見上げた。 「『神』とはなんだ。あなたのことか。ガンダルフの守護者よ。」 「いや、違う。私は『神』ではない。」 「だが、神殿やよその魔物はそう思っている。あなたは『神』と名乗らないのか?」 「私は『神』ではないから、そう名乗らないだけだ。だが、『神』という存在はいると信じている。」 「魔物は神に捨てられたもの。神ではなく、闇から創造されたもの、と言われている。本当のことは私にはわからない。なぜなら、私が気づいたときには、もうここにいたのだから。あなたは知っているのか、魔物がなぜ生まれるのか。」 |
|
|
|
考え深げに言う湖の魔物の風情は、かつての太古の人々を髣髴させるものがあった。そして、湖の魔物は、はっとするほど真摯な目で彼を見た。 「おまえ達は、魔物と呼ばれているが、『神』に捨てられたのもとは私は思わない。少なくとも私の信じている『神』なら、そう言われるだろう。まして、闇から創造されたものではない。ただ、ここの人間と呼ばれるものとは、いろいろな意味で違いがある、と言うだけのことだ。彼らの数が多いだけに、おまえ達はどうしても隅に追いやられているように見える。」 「ではなぜ、魔物がいるのだ?」 そんな話では納得がいかないという口調だった。 |
|
|
「魔物というが、おまえ達のほうこそ、本来このガンダルフに住んでいた者達に一番近いものなのだ。人間はよそから来たものに過ぎない。」 「本来ガンダルフに住んでいた者?それはどういうものなのだ?彼らはすべて魔物だったのか?」 「その時代には、魔物とは呼ばなかった。彼らしかいなかったからだ。今のここの人間達とは違い、おまえ達のように、遥かに寿命が長く、強く、賢い生き物だった。そして、たくさんの呪文を知っていた。彼らは、この星のほかにも多くの星があり、そこに様々な生き物がいることを知っていて、多くの知識を求めて、この星から出て行ったのだ。もちろん、この星に残ったものがいる。おまえ達魔物だ。そして、帰ってきたものもいる、あの人間達だ。だが、帰ってきたものの多くは以前のガンダルフの人々とは違っていた。」 |
|
|
|
「元は同じなのか?」 「そうだ。元は同じでも、おまえ達魔物と、人間とはだいぶ違ってしまった。そして、いがみ合うようになったのだ。私は、それが残念だ。おまえ達と人間とが形や力の差を越えて、新しいガンダルフを作っていくことが、私のたった一つの願いなのだ。だが、今のままではとてもそれは望めまい。」 |
|
|
湖の魔物にこの話が理解できたのだろうか、と話しながら彼は不安だった。彼には話し相手が必要なのだ。だが、ガンダルフを去った人々は、帰ってきたものがいても、以前とは違ってしまった。かつての太古の人々の記憶を保ってはいなかった。人間達はこの星にたどり着くのがやっとであったし、そのときの技術や知識も世代を超えるにしたがって、失われていった。 「私のような魔物と人間が一緒になるなど、とても考え付かぬ。…だが、いつかそんな日が来るのだろうか。」 湖の魔物は呟くようにいうと、静かに水の中に戻って行った。 彼は、湖を囲む山並みに日が落ちていくのを見ながら、湖の傍に佇んでいた。 |
|
|
|
湖から離れてしばらく行くと、町があり、その中心に大きなピラミッド型の神殿があった。 彼は、それを仰ぎ見て、なんとも言えない感慨が浮かんでくるのを抑えることができなかった。 かつては、多くの太陽エネルギーを吸収し、蓄積する目的で使っていたのだが、今神殿にいる神官と呼ばれる者達は本当の使い方など知らず、ただ建物としてだけ使っている。この建物も彼らが建てたものではなく、太古の人々が建てたものだった。 |
|
|
目を閉じると当時の様子が、現在のように蘇ってくる。もう何百万年も前になるというのに…。夜になると、ピラミッド型のこの建物は光り輝き、闇夜を明るく照らしていた。建物の構造自体がエネルギーを吸収しそれを一定の呪文で発散するように作られているのだ。今では夜になっても、かつてのように光ることはなくなっていた。人々がその呪文を忘れたためでもあるが、すでにそうしたものがあることさえ、忘却の彼方なのだ。 |
|
|
|
だが、神殿の神官はある呪文を使っている。神殿に属していると考えられているその呪文は、神殿に蓄えられたエネルギーによって、使用できる特殊なものだった。魔物たちは自分の力によって呪文を使うが、自身にそうした力のない神官達は知らず知らず、神殿に蓄えられたエネルギーを経験によって使っているのだ。 神殿を中心に栄えているその町は、トータムと言われていた。夕闇の中で、道を急ぐ人々がおり、神殿の下級神官が町の辻で、そうした者達を夕闇の中から現れるという魔物から守るように立っている。 |
|
|
神殿の神官はすべて独身者であり、神に仕え、人々を魔物から守るために存在していた。このあたりでは、神殿はかなり権威を持っていた。国としてのまとまりがゆるく、王と言う存在がいる地域といない地域があるが、合議制の集落の多いこのあたりでは何を決めるにも人々は神殿の神官を頼りにしていた。神殿には大きな図書館があり、トータムよりも大きな神殿には大神官がいる。大神官は本来は行政官ではないが、こうした地域では政治向きにもかなりの影響力をもっていた。その割には清貧を誇っており、不正などはあまり見られなかった。 |
|
|
|
彼は普通の人間に見えるように呪文をかけて身なりを変え、神殿に近づいた。神殿は人間にはいついかなるときも門を閉ざすことはなかった。困っている人や病人や老人を助け、親を失った子供の世話をするのも、彼らの仕事だった。 きれいに掃除された床にはチリひとつ落ちてはいない。神殿は多くの灯が灯されていて、明るかった。魔物は明かりを嫌うという迷信から、そうしているのだ。夜中、その灯は絶えることなく、点けられている。 |
|
|
奥のほうへ行くと、何体かの神像があった。昔にはなかったその神像は、神々しく神殿の広間にそびえたち、人間を見下ろしている。そのうちの一つに目を向けた彼は、ため息をついて苦笑いをした。その神像は、人間達がオリンエルブと呼ぶ天空の城に住むガウェン・レヴンの神像だった。神殿では彼すら、神の一人として考えられている。 もちろんそこには、太古より『神』として崇められていた「ウル」という、神の中の神という名で呼ばれている神像もあった。その神像はところどころ、欠けてきており、かなり古いもののようだった。彼の記憶によれば、それはこのピラミッドの建設当時からある、本物だった。着ているものや、顔の表情が太古の人々によく似て、懐かしい気がした。彼がここに来たのは、この神像を見たかったからだ。 |
|
|
|
「どうしました?」 突然、下級神官の一人が彼に尋ねた。どこか具合が悪いと思ったのだろうか? 「いいえ、別に何でもありません。少し、時間ができたので、神に祈りをしようとして参りました。」 「それは、よい心がけでございます。どちらから、おいでに?」 「湖の近くの村に住んでいます。今日はこちらにくる機会がありましたので、ちょっとこちらによって行こうと思いまして参りました。」 「そうでしたか。湖といえば、そちらには魔物がいると聞いていますが、ご家族は大丈夫ですか?」 「はい。おかげさまで、これまで無事に過ごしてきております。今日はそれのお礼も兼ねてまいりましたので…。」 |
|
|
「それは、まことに神のご加護でございましょう。私どもも、できるだけ魔物どもがいなくなるよう、常日頃努力しておりますが、なかなか彼らも悪賢く、まだまだ平らげるまでできないのが、大変残念です。」 「いいえ、神官の皆様のご苦労、いつも感謝しております。私どもがこうして無事に暮らせるのも、神と神官の皆様のおかげと思っております。」 と、少し悲しい思いで彼は言った。 神官はそれで満足したのか、彼から離れていった。 |
|
|
|
神像の前には祭壇があり、花が飾られ、何人かの神官が傍にいた。彼は、「ウル」と呼ばれる中央の神像の前に膝間づいた。下から見上げると、神像は巨大で厳しい感じがした。神官たちにとって、この「神」はどう考えられているのだろう。彼は祈りを捧げる振りをしながら、考えた。 元々、神殿は神殿として建てられたのではない。かつてはガンダルフに住む人々が多くのエネルギーを必要としていたので、その補助として太陽エネルギーを吸収して蓄積していたのだ。自分で持っている力以外にも、その力を必要とするときにこの建物から引き出して使っていたのだ。だから、多くの神像もなかったし、建物を維持管理する者だけがいただけだった。 |
|
|
時代が変わって、本来のガンダルフの人々が去り知識が失われた後、建物の維持管理をする人々だけは残っていた。彼らはすべてではないが、太古の人々の知識を保有していた。それを一部の人々にだけ、分け与えたのだ。呪文を使うには力がいる、だから、その頃まだ残っていた蓄積されたエネルギーを引き出すための呪文を彼らは教えたのだ。長らくそれは、この建物を維持管理する人々の間で細々と伝わっていた。だが、魔物と人間の区切りがはっきりするにつれ、その呪文は神殿の呪文として使われるようになった。神殿の呪文は魔物が使うものではなかったので、聖なる呪文、神にかかわる呪文と考えられるようになった。 やがて、神殿に神像が並び、神官たちが人間の間で権威を持つようになった。 |
|
|
|
神官は神に仕えるものと考えられていたから、世俗とは違い、その人格においても人々から尊敬されるような人物が多かった。だが、時代を経るにつれ、人間と対立する魔物を滅ぼすことをその仕事とするようになった。 この神殿の神官たちが流布する教えは、魔物を悪の象徴としている。魔物は殺人や盗みなどを好んで行い、人を騙し、人を食らうことまでする。だから、彼らは悪の象徴なのであり、滅ぼさなければならないものとしている。 これは、本当に「ウル」から来た教えなのだろうか? |
|
|
太古から神として崇められてきた「ウル」の神は、現在の人々の想像上のものにしかすぎなくなったのか。ここの人間達も「ウル」を想像しただけなのか。であったとしたら、太古の知識を失った今でさえなぜ同じ名の神をどうして想像するのか。それに、神官の中には確かにそうした「神」と交信ができるというものもいた。それなのに、なぜ、太古の人々が聞いたものとは違う教えが流布されているのか。 太古の人々の聞いた教えは、宇宙には様々な種族がいて、その形状や能力がどんなに違っていても、確かに彼らは神の作られたものなのだ、ということだった。だから、決して争いを起こさないようにと。そうした種族は我々とは違った考えをもっているかもしれない。だが、そうだとしても同じ神から作られたものなのだから、理解することが可能である、という教えだった。 |
|
|
|
だが、現在の神殿の教えはそれとは違っていた。ガンダルフに住む者を、魔物と人間とに分け、人間は神の作られた者。魔物は神ではない、闇から生まれた者だから、滅ぼさなければならないというのだ。そして、魔物と呼ばれる者たちを人間の社会から追い出し、決して中には入れない。 その結果、魔物は人間を憎むようになった。また、自分達は人間とは違うのだから、価値観やモラルも人間と違って当たり前だと考えるようになった。人間の持つ文化や伝統も嫌い、人間社会の外で、まるで動物のように森や洞窟に住んでいる。その上、人間を傷つけることも当たり前のように思うようになったのだ。 |
|
|
これは、ガンダルフに住む人々が堕落した、以前の段階よりも下がったということではないだろうか、と彼は考える。宇宙を知らない、太古の人々よりも知識のない人々や魔物がそうなるのは仕方のないことなのだろうか。これからガンダルフがどうなるか、どこへ行こうとしているのか、彼は不安だった。新しい移住者が来たとして、彼らとも果たしてうまくやっていけるのだろうか。 だが、もっと心配なことがあった。 |
|
|
|
太古の時代には、この銀河には宇宙航行種族はほんの三種族を数えるのみだった。今ではそれが、何十種族と増えている。当然、彼らの中には争いを繰り返し、他の種族を支配するような考えを持ったものもいる。そうした中で、ガンダルフの人々はこのままでいいのだろうか。 彼はまだ決めかねていた。考えれば考えるほど、わからなくなる。どうすれば、このガンダルフにとって最もよい判断になるだろうか。彼は、神殿で初めて真摯に祈った。 (私は、どうすればよいのでしょうか。) 神殿の外では暗い帳が訪れていた。だが、神殿の中は明るく灯が燈され続けていた。 |
|
|
神官の一人テルリは灯明の油を足しに、神像の間へやってきた。テルリは下級神官だった。 神像の前の他の上級神官の前を頭を下げながら通り、神像の前の灯へ油を足した時、少し離れたところで祈りをしている人影を見た。信仰心の厚そうなその人は、一心に神に祈りを捧げているように見えた。その姿に見とれていると、その人の姿から次第に光がはみ出してくるのが見えた。その姿全体が淡い光に囲まれ、だんだんその光がはっきりとしてくる。 あれは誰なのだろうか?テルリは思った。まさか魔物ではあるまい。神殿の中なのだから。だとすると人間か? |
|
|
彼は自分に神と交信する能力のないのを不甲斐なく思った。それさえできれば、このようなときにもどれほど助けになるか。ガンダルフに古くからある、呪文にもそのようなものは見当たらないし、聞いたこともない。ここに来たのは、ウルの神像があるからだった。あの天空の城には「ウル」の神像はない。祈るには、やはり神像のような対象物があったほうがやりやすいような気がしたのだ。 神に対する時は、天空の城のガンダルフの守護者と呼ばれる彼であっても、地上の人間達と大して変わらない。祈るしか術がない。そして、その答えはいつ、どのように得られるのだろうか。 |
|
|
|
彼は自分のためではなく、ガンダフルのために祈った。自分のことであれば、祈る必要もない。大抵のことは自分の力でできる。だが、今回はそうはいかない。他の惑星からの移住者の受け入れという、このような重大な決断をするのは初めてだった。これはガンダルフの現在生きている人々だけではなく、未来のガンダルフの人々にもかかわりのあることなのだ。 テルリは、驚いていた。その人間から発する光はやがてウルの神像に届くほどになった。すると、ウルの神像から、もっと強い光がその人間に降り注いだのだ。テルリは周りを見回した。だれか見ていないかと思ったのだ。だが、だれもそのことに気づいた者はいないようだった。神像の傍にいる上級神官たちは何もなかったように、佇んでいる。 |
|
|
彼が求めているのは、「ウル」からの確かな答えだった。声でも言葉でもどちらでもいいから、自分の心の中に浮かんで来て欲しいと切実に願っていた。 「どうしたのだ、テルリ?」 上級神官のトフタが通りかかって、じっと神像の前に座る者を見ているテルリに気づいて尋ねた。 「見てください。あの者を。あの者から光が出ているのです。そして、あの「ウル」の神像からも光が出ているのです。まるで、人間ではないような、もしかしてあれは……。」 |
|
|
|
トフタは彼を見た。トフタにもテルリの言う光が見えた。トフタにはそうしたものを見る能力があった。人々はそれを神殿の力の一部だと考えていた。そうした力を持つものがやがて大神官となる資格をもっているのだ。 以前トフタは似たような光景を見たことがあった。あれは、いつのことだったか。おそらく子供の頃、何十年か前のことだった。目の前の人物はあの時の人物と同じように見える。年もとっていないように、それとも同じ血族のものだろうか。だが、もしかしたら……。 |
|
|
当時の神官の一人、ゴレンはトフタの話を聞いて、それは天空の城の主、ガウェン・レブンに違いないといった。自らの身体から光を発するのは神の光を身に呈しているからであるというのだ。ガウェン・レブンは不老不死でガンダルフの守護をする「神」の一人である。それがなぜ今ここに来ているのだろうか。 彼の祈りは長かった。どうしても、「ウル」からの答えが欲しかったので、それがわかるまで祈り続けるつもりだったのだ。 |
|
![]()
|
|
明け方、彼は目を開いて立ち上がった。 「もし、ずいぶん長い間祈りを捧げておいででしたが、何を祈っておられたのです?」 と、トフタは近寄ってきて尋ねた。 「私には、難しすぎる問題を解決するために祈っていたのです。」 と、彼は言った。 「ほう、『神』は答えてくださいましたか?」 「いえ、ですが、まだ時間があります。もう少し待ってみようと思います。」 「それでは、しばらくこちらに泊まられてはいかがですか?」 「こちらに?いえ、そのようなご迷惑はかけられません。」 「大丈夫です。このトータスの町の神殿は巡礼に来るものが多く、宿泊する施設がありますので、よろしかったらご案内いたしましょう。」 |
|
|
彼は逡巡したが、やがて 「それでしたら、こちらに泊まらせていただきます。」 と言った。 トフタは彼に興味があった。彼が何者なのか、なぜ祈っていたのか。そして、あの光は何なのか。本当に伝説にある天空の城の主なのか。 |
|
|
|
彼は目の前の神官に、何か彼に意図があることを気づいていた。それが何であるかわからなかったが。それが、ここにとどまる理由でもあった。しかし、人間の住む町に長くいることは初めてだった。たまに来ることはあっても、ほんの数時間見て回るだけだった。今の人間のことにあまり興味を持つことがなかったのだ。かつてより格段に文明が低くなっていると感じるのはあまり楽しいことではなかったからだ。ただ、先ほどの湖の魔物との話で今までにないことを見つけただけに、人間ともなにか新しいことが見つかるのではないかと思っていた。 |
![]()
|
|
神殿の中の付属する施設を見るのは、彼には初めてだった。どこも作りは質素だったが、きれいに掃除されていた。 神殿の神官は下級神官・上級神官を問わず、皆白いローブを着ていた。下級神官は誰でも親切で、上級神官は少し居丈高な気がするのは、気のせいだろうか。 彼の案内された部屋は寝台が一つと、椅子と小さな机がある狭い部屋だった。彼は寝台に座ると、目を閉じた。彼は祈るのではなく、この神殿に向かって尋ねた。 (おまえは、誰だ?) |
|
|
|
すると、神殿が一瞬震えたように感じた。 (私はトータム、エネルギーを管理する者。あなたは誰だ?創造者か?) と、声なき声が彼の心に響いた。この建物には管理するシステムがある。何百万年もの歳月に一度たりとも休まずに、動いているのだ。彼はそれを確認すると、 (そうだ。私はオリンエルブに住むもの。) と答え、システムの記録の部分に入った。 記録の部分にはここ最近のトータムについて、様々なことが記録されていた。簡単に言えば、トータムの歴史である。どのように建物が神殿と呼ばれるようになり、神官がどのように作られたか。 |
|
|
この大陸には多くの神殿が残っていた。大小千位になるだろうか。そして、神官たちも多く、この大陸の政治向きにも大きな影響力をもっていた。それゆえ、王を頂点とする国は海に近い場所にしかできなかった。 大陸を大きく東西南北に分け、その一つ一つに、さらに大きな神殿が存在する。かつてはエネルギーを統括する役目を負っていたその建物は、今は大神殿と呼ばれ、大神官が住んでいる。その大神官は大神殿のエネルギーを使用する多くの呪文を知っているのだ。それは代々受け継がれ、今に至っている。それゆえ、大神官は他の神官をしのぐ力を持っており、大神殿のエネルギーを使用する様々な呪文を駆使できる。 |
|
|
|
普通の神殿の呪文は、その神殿のエネルギーしか使えないが、大神殿では管轄する中小の神殿のエネルギーを統括しているので、そのすべてを使えるのだ。 その力故に大神官は他国との争いを治めたり、強い魔物を消滅させることができ、多くの人々から尊敬を受けている。その権勢は絶大なものがある。だが、彼らは本当のことを知らない。その力が本当は何なのかを、知らないのだ。 ここは大陸の南にあり、カリガムという大神殿がこのあたりを支配している。人々が金ではなく、供物という形で税金を納め、それを基にして様々な活動をしている。神殿の活動の中心は魔物の退治にあったが、それだけではなく、病人を診たり、老人を助けたり、孤児を世話したりなど、本来政治がするようなことを代行していた。 |
|
|
大神殿では時代が下がるにつれて富を蓄積するようになり、それを使って最近は学校の経営などもしているようだった。ただ、神官は独身者が基本であり、ある家系がそれを独占するなどということはなかったので、人々からはその公平さと清新さを認められ、尊敬されていた。 彼は、神殿そのものが間違っているとは思わなかった。ただ、なぜ神官たちが魔物を退治するのを当然と思うようになったのかが分からなかった。それは、いつからなのか。魔物の存在と人間の存在が対立するようになったのはなぜなのか。 以前何度も、そのことについて、各地の神殿を調査したことがある。その記録を検証したのだ。だが、分からなかった。それはなぞだった。 |
|
|
|
ただいつの頃からか、「神」からの啓示として、魔物という言葉が出てくるようになった。 人間と魔物が、というよりは本来ガンダルフの人々の直系の末裔である魔物が、人間と区別され、その尊厳を失った理由とは何か。 彼がその答えを知るために、今まで様々な魔物や人間に会っていた。その中で次第に、この大陸で最も古い魔物といわれている森に住む魔物、マルトに住むもの、もしかしたら、それが何かを知っているかも知れないと思うようになった。 だが、今はそれよりも大事なことがある。新しい移住者の受け入れの決断である。それは、とても一人で考えて決断できることとは思えなかった。誰かに相談したかったが、そんなものなどいない。今太古からの存在でこのガンダルフに残っているのは、彼一人のみなのである。 |
|
|
もし『ウル』と名乗るあの太古からの神に答えを聞くことができたならと思い、彼はこの神殿までやってきたのだ。もちろん、ここに『ウル』の神がいるわけではない。たが、『ウル』と呼ばれる神の像があるということ、それも太古から損壊を免れてあるということに、彼は神の何らかの意思を感じていたのだ。 神との交信ができるものは、この神殿にもいるかもしれない。それは、天空の城に残っている呪文の知識とは別物なのだった。神との交信に呪文を使ったという記録は、彼は知らない。そうした能力を持ったものは本当に希少な存在であったし、その能力を後世に伝えることもできなかった。 |
|
|
|
だが、そうした能力を持ったものは、このガンダルフに今もいる。そうした者がこの神殿にいるということを、彼は知っていた。神官の中にそうした力を持っているものが稀にいるのだ。 |
![]()
|
|
日が高くなってから、彼は食堂に行ってみた。 神官たちはすでに食事を終えていたようで、ほとんど姿はなかった。数人の巡礼者がいたが、家族とともに食事をしていた。 彼は食事を済ませると、神像の間へ再び入った。昨夕彼が入ったときと同様、数人の神官が神像の前で瞑想をしていた。他に、巡礼者か町の者のような一団がいた。彼らは一様に決まった祈りの一節を唱和していた。 彼は、ふと天井を見上げた。神像の間の天井近くに、回廊があった。そこは誰もいなかった。明るい陽が降り注ぐ、その回廊は立ち入り禁止ではないようだった。上に行く階段を探していると、昨夕の神官にであった。 |
|
|
|
「どうしました?」 「実は、天井近くにある回廊へ上りたくて、階段を探しているのですが。」 「ああ、それでしたら、あちらの方に上に行く階段があります。」 「あの、上ってもよろしいのですか?」 「もちろん。かまいません。神像をよく見るために近くに行きたいという方も居られます。夜は危ないので上れませんが、昼間は上ってもよいことになっています。」 その神官は不案内な彼を案じて、案内しましょうと言って、一緒についてきた。 「あなたは、どちらからいらしたのですか?」 と、若いその神官は尋ねた。 |
|
|
「湖の近くの村からです。」 「そうですか。実はきのう、不思議なものを見たのです。」 「不思議なもの?」 「ええ、初めてでした。夕闇の中、この回廊に立っていると、湖の方から、光が来るのが見えたのです。」 「魔物ですか?」 「いいえ、魔物なら、あのような光を帯びることなどありません。魔物は闇に属する者。あれは確かに光でした。神に属するものです。」 「それは、どこへ行ったのです。」 「この神殿に来たのです。」 「この神殿に?」 「ええ、そのあと、私は仕事で神像の間へ入りました。そうしたら、その光と同じものが見えたのです。よく見ると、それは人でした。人から光が出ていたのです。」 「それで…。」 |
|
|
|
彼も興味を持って尋ねた。もしかしたら、彼が来たのにあわせて何か、神が印を見せてくれたのかもしれない。 「その人は、その……。『ウル』の神像の前で祈っていました。あなたです。あなたから、光が出ていたのです。」 「……!」 信じられないという目で、彼は神官を見た。 「まさか、あなたは私をからかっているのではありませんか。」 彼は自分がそうした光を出していることなど、気づいたことはなかった。 「見たのは私だけではありません。上級神官の一人も見えたと言いました。本当の事です。」 |
|
|
この神官はもしかしたら、あの力を持っているのかも知れないと彼は思った。本人はそれに気づいていないのかも知れないが。 「あなたは、いつもそうしたものが見えるのですか?」 と、彼は尋ねた。 「ええ、小さい頃から。私だけではなく、神官の中にはそうした人が時折いると聞いています。」 「それは、何か他に特別なもの、例えば、神の声が聞こえるとか、そうしたこともできるのですか?」 「まさか。私は、見えるだけです。声が聞こえたことはありません。」 「神官の中には、声が聞こえる方も居られるのですか?」 |
|
|
|
「昔、そうした神官がいたということは聞いています。それより、あなたはどうなのです?昨日は祈るあなたの身体から光が出ていましたが、それに答えるように神像のほうからも光が出ていたのです。何か声を聞きませんでしたか?」 彼は、一瞬耳を疑った。 「何ですって?もう一度言っていただけませんか。」 「ですから、昨日あなたが祈っていたとき、身体から光が出ていたのです。そうしたら、まるでそれに答えるように神像の方からも光が出てきたのです。」 いったいそれはどういうことなのだろうか、と彼は考えた。祈っているとき、何の声も聞こえなかったし、何の変化もしなかったはず。 「信じられない……。」 彼は信じられぬ思いで、日の降り注ぐ回廊を見上げた。 |
|
|
トータムの神殿の上に位置するのは、カリガムの大神殿だった。 カリガムの大神殿はその下にトータムを含めた大小数千もの神殿を従えている。それらの大神殿を統括するのがカリガムの大神殿であり、カリガムの大神官グルスだった。 グルスはトータムから今日届いた至急便に目を通していた。トータムの神殿に天空の城の守護者が現れたというのだ。 |
|
|
天空の城、オリンエルブの守護者が地上に現れるのは、何十年ぶりだろうか。そのたびに神殿の者達はその知らせをカリガムの大神官に送っていた。特に、トータムによく現れるというのが昔からの言い伝えである。その理由はわからないのだが、他の神殿に現れたというのは、ついぞ聞いたことはない。 グルスはため息をついた。これは何の印なのだろうか。何かこれから起きるというのだろうか。ともかく、観察を怠らぬよう、神殿の神官たちに言い含めてある。 |
|
|
|
部屋の扉をたたく音に、グルスは振り返った。 「入れ。」 入ってきたのは、上級神官のドイルだった。 「何かね。」 「はい。アイルから助力の要請がありましたので。」 「アイル?あの、マルトの森に住むとかいう、魔物退治の話か。」 「はい。あの魔物は大変力が強く、アイルの者達だけでは心もとないということなので、誰をやりましょうか。」 「ふむ。私が行ってもよいのだが、…。」 |
|
|
「いえ、大神官様がおいでになるほどでは、たかが魔物退治ですから。」 「だが、マルトの森に住まうというあの魔物は、かつてアイルの上の神殿の上級神官が行ったとき、命からがら戻ったと言うではないか。」 「はい。ですが、大神官様がおいでになるというのは、どういうものでしょうか。」 はっきり言えば、不安なのだった。ドイルはもし大神官でさえ、あのマルトの森の魔物にかなわないということになったら、住民達に何と思われるかということを案じていたのだ。 「私の力では足りないか?」 |
|
|
|
グルスはドイルの心配を理解していた。このところ、あちこちの大神殿の力が失われつつあるという、噂がたっていたのだ。 それは、ある意味で事実だった。大神官はかつてのような大きな奇跡を出す力がない。 だが、それがなぜなのか、誰にもわからなかった。 神殿が「神」の力を失いつつある、ということが明らかになったとしたら、この世界はどうなるのだろう。いまだ魔物が跋扈するこの世界では神殿の力は不可欠だというのに。 それとも、神殿のやっていることが「神」の意にかなわないのだろうか? 時折、グルスはそんな思いに捕らわれることがある。 |
|
|
「ドイル。マルトの森はトータムの神殿に近いか?」 「トータムからですか?近いというよりは、もし御用があれば、マルトの森に行くときにそこによっていくことは可能です。」 「そうか。それならば、ドイル、おまえがマルトの森に行きなさい。私は、トータムまで出向くことにする。場合によっては、その後おまえとともにマルトへ行く。」 「大神官。トータムに何の御用なのですか?」 「知らせがあった。トータムに天空の城の守護者が現れたと。私は会ってみたいのだ。この地上に現れるただ一人の神に。」 ドイルは小さく頷いた。 |
|
![]()
|
|
彼はまた、神殿の神像の前で祈っていた。 あの神官の言っていたことが、本当なのかはわからない。だが、やはりここには何かあるのだ。彼はそう感じていた。 「ウル」の神像は彼から見て、何の変化もない。古い神像は度重なる天災や自然の猛威に耐えて、ここに存在している。この神像が作られて何百万年も経つのだ。 ここに神像が作られたとき、ここは神殿ではなかった。しかし、今は神殿と言われ、多くの人々の信仰を集めている。それは、ここに神像があったからなのだろうか。 多くのこうした神殿と呼ばれるものの中で、なぜここは「ウル」の奇跡を見るものがいるのだろうか。 |
|
|
各地にある神殿にはここと同様たくさんの神像がある。「ウル」の神像も各地にあるのだ。けれども、他の神殿で「ウル」の奇跡の光を見ることのできる神官はいないし、その光があるのかもわからない。 太古からこの星を見守ってきた彼、ガウェン・レヴンでさえ知らない何かがここにはあるのだ。 |
|
![]()
|
|
天空の城の中を、リーラは一人歩き回っていた。城の中は広かった。たくさんの棚のある部屋、置物のある部屋などがあるが、不思議なことにそこには生き物が住んでいるような生活の気配がまるでなかった。 ここにはガンダルフの守護者といわれるあのガウェン・レヴンしか住んでいないからなのか。それは、ひどく孤独な寂しい場所に思えた。 何万年、何百万年とこの広い城で、仲間の帰りを待ちながら、あの星を見て暮らすなどリーラにはできそうも無い。 |
|
|
この城を作り、星を旅した太古の人々はいったいどこへ行ってしまったのだろう。そして、ここに彼はなぜ一人残ったのだろうか。 リーラは広間のあの彼のいた窓から、ガンダルフを見下ろした。あの星のどこで、今、彼は何をしているのだろうか。突然やってきた、移住者の問題にどう答えを得ようとしているのだろうか。答えを出すのに、あとひと月の時間が欲しいといったときの、彼の顔がリーラの脳裏に浮かんだ。 今や彼はたった一人でその答えを出さねばならないのだ。この下の星に何億人住んでいようと、彼らに相談などできるはずも無い。 |
|
|
|
今のガンダルフの文明程度では、他の天体に生物が住んでいることさえ理解できないだろう。ほんの少し外見が違うだけで、魔物だと言われかねない世界で、もしそうだと思われたら命さえ危ういのだ。 こんな星に移住しなければならないとは、とリーラはため息をついた。この銀河には他に宇宙航行の技術を持った種族もいる。そうした種族のいる星をなぜ、アロミアの長老達は選ばなかったのだろうか。 まだこの銀河宇宙に来たばかりで状況がわからないにしても、もっとましな星はないのだろうか、とリーラは考える。 見上げれば、窓の外の惑星ガンダルフの上には、無数の星々が輝いていた。 |
![]()
|
|
トータムの神殿では騒ぎが起きていた。 突然カリガムの大神殿の大神官がおいでになるという連絡がもたらされたのだ。早馬でやってきた伝令は、よろめく足取りで神殿の階段を駆け上がった。 トータムの神殿を司っている神官の長タムズは、いったい何が起きたのだろうと驚いていた。大神殿の大神官がおいでになるとは十年に一度もないような大事だった。カリガムの大神官が前にみえたのは三十年ほど前のことになる。そのときは、百年に一度のトータム神殿の大祭が行われた年だった。 |
|
|
|
トータムの神殿では、他の神殿とは違い、百年を一区切りとして大祭が行われるのが習慣だった。それはここ五千年続いた神事でもあり、大神殿でも行われないような大祭である。その縁起は、トータムがカリガムなどの大神殿よりも古くから存在するという謂われからきていた。それが真実のことであるかは、今となっては知る人も根拠もないのだが、長い間大祭の習慣は途切れることなく続けられてきたのだった。 「で、いつごろ、大神官はお立ち寄りになるのかね。」 できるだけ落ち着いた様子を保ちながら、タムズは伝令を取りついだ神官に尋ねた。 「早ければ、三日後ということでした。」 カリガムからトータムまでの時間としては妥当だった。 |
|
|
「わかりました。では、大神官を迎える支度を整えるよう、他の神官達に伝えなさい。」 もしかしたら、とタムズは思った。トータムで起きたことと、何か関係があるかもしれない。まだはっきりとはしないのだが、あの天空の城の守護者がこのトータムに現れたというのだ。それらしき者を神官が見たというのだ。 天空の守護者ガウェン・レヴンが現れるのは、決まってトータムの神殿だというのが、昔からの神官の間の暗黙の了解事項なのだった。これは知識としてではなく、口頭で見た神官から告げられるもので、確かなことかどうかはわからない。 そうでなければ、大神官がこのたいして重要性のないトータムに来るという理由がわからない。 |
|
|
|
トータムは繁華な町ではないし、特にこれといった産物も無い、普通の だが、トータムという場所は他にはない何かがある、という不思議な感覚があった。百年に一度ある大祭もそれである。他に同じような習慣を持つ神殿など聞いたことが無い。なぜ、トータムにそれがあるのか、それは遥かな昔にとうに忘れられてしまった何かが関係しているのではないかと、タムズは考えることがある。 それに、天空の城の守護者を見ることができる者がトータムにいる、ということも何かを暗示しているように感じる。 |
|
|
神殿がにわかに騒がしくなったように感じられた。 彼は、神殿の地下にあるシステムに尋ねた。 (何事が起きているのか?) (カリガムから大神官が来るようです。) (大神官?…) 今年はトータムの大祭がある年ではない。それなのに、何の用なのだろうか。何にしても、厄介なことだ。静かに考え事をしていたいときに。 騒ぎにまぎれるようにして、彼は神殿から姿を消した。彼は大神官などに興味は無いのだった。 |
|
|
大神官の行列は、街道に長く続いていた。馬や荷物を載せた馬車が続き、お付きの神官も大勢従えて、静々と行列が動いている。街道には他に人の姿は無く、そんな行列が通っても大して迷惑にはならない。 もともとトータムやカリガムの神殿を要するタントス大陸の南の地ヘイスは、たいして繁華な町はない。海に近い場所は、もう一つの大陸エゼキルの諸都市と交易をして繁栄しているが、内陸部はいたって寂しい。ヘイスには魔物が棲むという湖があるため、人が住みにくいのだった。大神官の行列も湖を避ける道をとっている。 と、大神官の行列が止まった。神官が馬を下りて口々に何かを叫んでいる。その指先が天を指していた。 |
|
|
|
それは突然出現した黒い竜巻だった。 その竜巻は一瞬にして、大神官の行列を空に巻き上げると何処かへ消えた。その後にはその竜巻を免れた一握りの神官が、呆けたように空を見上げる姿が残されていた。 「湖の魔物だ。やつに違いない。」 と、誰かが叫んだ。 |
|
|
そのタントスの南の地ヘイスで起きた突然の竜巻は、天空の城オリンエルブからよく見えた。 「あれは?何かしら…」 ガンダルフの地上を見下ろしていたリーラはその竜巻に気づいた。何か黒いものがおそらく大気圏の下の方を移動している。だが、そこに竜巻が起きるような気象条件はない。ヘイスには雲ひとつ無い真っ青な青空が広がっているはずなのだ。 一瞬でリーラは竜巻のあった場所に移動してきた。竜巻はすでに無く、数人の人影が騒いでいるだけだった。 おかしい、とリーラは思った。そこに微かながら、悪意が残っていた。ガンダルフの人間を呪うような想念だ。 |
|
|
|
「何をしている?」 天空の城にいったん戻った彼は、リーラの姿が消えているのに気づいて、追ってきたのだった。 「ここに、竜巻が起きて、人を空に巻き上げて行ったらしいわ。」 「何?ここは、ヘイス。トータムの神殿の近くだ。それでは巻き込まれたのは、カリガムの大神官の行列か。」 彼はトータムの神殿で聞いたことを思い出していた。 「あれは自然の竜巻ではないわ。何か魔物が起こしたものでしょうね。」 と、リーラが言った。 |
|
|
彼は竜巻を起こすほどの魔物には心当たりがあった。 「この近くには湖の魔物がいるようだけれど、その魔物かしら。」 「いや、まさか…。」 彼には湖の魔物が直接自分に危害を加えない者に対してまで、何かをするとは思えなかった。だが、竜巻を起こすとなると、相当力のある者でなければできない。 「行ってみましょう。そして聞いてみるのよ。たまには犯人探しも面白いわ。」 暇つぶしにはもってこいというような言い方が、彼の気に障った。だが、リーラは頓着しなかった。 |
|
|
|
湖に着くと、目の前に神官のなりをした何十人もの人間が倒れていた。人間だけでなく、荷物も四散している。 「これは…。」 あまりの状況に彼は絶句した。 人間達は倒れているだけではなかった。傷を負っている。竜巻から投げ出されたときに怪我をしたのだろうか。 リーラは用心深くあたりを窺っている。 そのうちに、湖が波立って、魔物が姿を現した。彼がやってきたのに気づいたのだ。 「これは、おまえがやったのか?」 と、彼は湖の魔物に尋ねた。 |
|
|
「これは!」 一瞬、あたりの状況に驚いて、 「一体何があったのだ。だいたい、この辺は神官どもは避けて通るはず。」 と、湖の魔物は呟くように言った。 「竜巻よ。黒い竜巻があの神官たちをここへ落としたのよ。その竜巻を見なかった?」 と、リーラが尋ねた。 「おまえはだれだ?人間か?」 「私はリーラ、よそ者よ。でも、彼を知っているのでね。」 リーラは彼を見上げた。 「おかしいわね。あなたの波長と違うわ。あの竜巻は人間に対する憎しみが詰まっていた。それはあなたの持つものとは、少し違うようね。」 と、リーラは言った。 「竜巻だと?近頃そんなことが起きたことはない。」 |
|
|
|
ヘイスの地は穏やかな気候で、めったに竜巻などは起こらない。 「あれは、おまえがやったのではないのか?」 彼は横倒しになっている神官達を眺めて尋ねた。 「違う。私ではない。」 「でも、あれは普通の竜巻ではなかったわ。一体誰がやったのかしら。それにあの神官たちは何をしにここへきたのかしら。あなたは知っていて?」 彼はトータムの神殿で聞いたことを思い出そうとしていた。カリガムの大神官達の本当の目的は、彼にあったことは感じていた。だが、表向きは何だと話していたか? 「あの、神官達はカリガムの大神殿からきた者達だ。トータムには何か用事があったのだろう。そうだ、トータムはただの寄り道に過ぎない。本当は、マーダムの森に行くつもりだったのだ。」 「マーダムだと。奴か。あ奴はここまで、私の領域まで来て竜巻を起こしたというのか。」 と、湖の魔物は言った。 |
|
|
リーラは先ほどの竜巻を思い出していた。あれは何かがいた。黒い渦巻きの中心に人間に対する強い憎しみを持つもの、それがこのことを引き起こしたのだ。 「このままでは、これをしたのはあなたの所為だと思われてしまう。それが目的なのかしらね。」 と、リーラは言った。 「これが、私のやったことだと思われるだと?」 と、湖の魔物が言った。 |
|
|
|
「そう。だって、あの神官達の前へ行って、自分じゃないと言えるの?それに、それをあの連中が信じると思う?」 「ふん、なぜ私がそんなことをしなければならぬ。」 「ほらほら、できないでしょう。あなたは、人間が嫌いだものね。」 ムっとして、湖の魔物は黙った。一体この人間は何者なのだ。魔物を見ても怖がらない。天空の城のガウェン・レヴンの知り合いだというのなら、普通の人間ではないということか。 「ともかく、トータムの神官にこのことを知らせなければ、…。」 と、彼は言った。 |
|
|
倒れている神官たちは、怪我をしているが命は別状ないように見えた。 リーラは、一人の神官の傍により、そっと息を吹きかけた。すると、その神官は息を吹き返し、起き上がった。その神官は傍に誰がいるのかも気にかけず、あわててトータムの神殿のある方に走っていった。 「これでいいわ。彼が知らせれば、大丈夫でしょう。」 とリーラが言った。 「何をした?」 と、彼は尋ねた。 |
|
|
|
「それよりも、他の者達の怪我を治さなければ、だいぶひどい人もいるようだし、…。」 「怪我を治す?そんなことができるのか、おまえに…。」 と、湖の魔物が驚いたように言った。 彼は、彼らグリトスの者達のことを何もしらないことに、その時気がついた。 グリトスの人々は特殊な力を持つものは少ないというが、彼には思いもよらない力を持った者もいるようだった。 太古のガンダルフの人々でさえ、怪我を治すようなことはしたことが無い。そんなことができると考えたことも無いのだ。 |
|
|
リーラという少女は倒れている神官達の傍により、手をかざしていた。すると、傷が薄くなり、消えていくのが見える。 「あの子は何者なのだ。」 湖の魔物は、得たいの知れぬ者を見た驚きを隠さなかった。まるで本物の魔物を見たというような表情だ。 「あの者は遠いところから来た。私の知っているのはそれだけだ。」 と、彼は言った。 グリトスという人々がどのような人々か、彼は初めて興味を持った。遠くから来ただけあって、考え方もすることも、おそらく自分とはかなり違うものがあるのではないか。彼らがガンダルフに住むとなると、その影響はどれほどになるのだろう。 |
|
|
|
トータムの神殿から人が来たのは夕方近くなってからだった。 倒れているカリガムの神官達を助けると、四散した荷物を集め、なんとか神殿へと帰っていった。だが、彼らは一人残らず、湖の方を胡散臭げに見るのを止めなかった。 竜巻にあって、別れ別れになったほかの神官達がトータムに着いたのは、それから三日後のことで、竜巻に巻き上げられた者たちが助けられていたことを奇跡だと喜んでいた。 |
|
|
カリガムの大神官グルスはトータムの神殿の神官長の部屋に入ると、 「世話を掛けた。竜巻にあったときはどうなることかと思ったが、皆無事にそろったようだ。」 と言って、グルスをねぎらった。 「このたびは誠に大変なめに会われました。ですが、無事に到着されたことを我々一同喜んでおります。」 と、タムズは言った。 「あの竜巻は、やはり湖の魔物がやったのだろうか。」 と、グルスは尋ねた。 |
|
|
|
「おそらく、そうではないかと。このあたりで、あれほどの力を持つ魔物は他に知りません。」 「しかし、なぜ、我々を狙ったのだ?」 「大神官がトータムにこられるのは、湖の魔物退治のためと思ったのではないでしょうか。」 何の証拠もあるわけではない。だが、他に何の理由があるのだろうか。他に誰がそんなことをすることができるのか。 「だが、我々は誰も怪我をしていなかった。」 と、グルスは言った。 |
|
|
それが不思議だった。トータムの神官が来たとき、誰も怪我をした者はなかったのだ。もし、湖の魔物が自分を退治しに来たと思うならば、怪我をするぐらいでは済むまい。命を失っても不思議ではない。でも、湖の魔物はそうはしなかった。それはなぜなのだろうか。 「理由はわかりません。第一、あの湖に棲む魔物が人間に何かをしたことなどほとんどないのです。」 人間達は湖の魔物を恐れているが、人間が何かをしない限り、湖の魔物は何もしなかった。今回は、こちらが何もしないのに手を出したことになる。 |
|
|
|
「ところで、例の人物のことだが、…。」 と、グルスは話題を変えた。 「それが、この騒ぎのためか、所在が分からないのです。騒ぎが起きる前は確かに居られたのですが、騒ぎの後は誰もその姿を見ていません。」 と、タムズは答えた。 「そうか、残念だな。」 「しかし、また現れるかもしれません。」 「いつかはな。」 グルスはどうしても聞かなければならないことがあったのだ。 |
![]()
|
|
トータムの神殿の周りに、たいまつを持った人々が集まり始めていた。 人々は不安になったのだ。今までおとなしかった湖の魔物がカリガムの大神官の一行を襲ったという話は、口伝にあっという間に広まっていた。 「何とかしなければ…。」 「今まで何もしなかったというのが、おかしな話だ。」 「これからは、何をするか分からんぞ。」 その不安は神殿の力が失われつつあるという、噂とともに尾ひれをつけて広がっていった。神殿の力が本当に失われてしまうのなら、人間達はどうすればいいのだろう。誰が、人間を守ってくれるのだ。 たが、その人間達の背後に何か黒い別のものの気配が漂っていた。 |
|
![]()
|
|
「いつまで、ここにいるつもりだ?」 と、湖の魔物が、リーラに言った。 「気になることがあるの。」 リーラは星空を見上げて言った。カリガムの大神官がトータムの人々に迎えられて去った後も、なぜかリーラは湖の傍に留まっていた。いやな予感がするのだ。これから何かが起こりそうだった。 「私のことは気にしないで。ここの人間達には私の姿は見えないから。」 この三日というもの、リーラはあたりをふらふらと動き回っていた。見たことの無い衣装を着ているし、ガンダルフの人間とは所作が違うので、湖の魔物は気になって仕方が無い。 |
|
|
「その変わった身なりは何だ?」 と、湖の魔物は言った。 「これは、私の国の衣装よ。あなたが人間の着る物に興味があるとは思わなかった。」 と、リーラは言った。 「ここヘイスでは、そんなものを着たものなどいない。」 「私から見れば、あなたの着ているものだって、変だわ。」 「人間でもないというのか?」 「あら、私は人間よ。そうでしょう。」 |
|
|
|
そう言われると、湖の魔物は黙ってしまう。確かに、人間としか感じられないのが、不思議だった。人間のはずが無い。あんな、怪我を治す力など、人間には無い。いや、魔物にだって無い。一体この娘は何者なんだ。 ガウェン・レヴンは、二人の会話をため息をつきながら聞いていた。まったく、このグリトスの娘は、何者にも何事にも頓着しない。 だが、この娘はなぜここを離れようとしないのか。彼はその理由が分からなかった。妙な胸騒ぎを感じるが、それが何なのかはわからない。ガンダルフは平穏な星のはずなのに、どこか今は変だった。彼らグリトスの者たちが来たからだろうか。 |
|
|
その時、遠くに松明の輝きが動くのに彼は気づいた。 「あれは、何だ?」 と、湖の魔物は言った。 「来たわね。」 と、リーラはまるで待っていたように言った。 |
|
![]()
|
|
それは少しずつ、少しずつ溜まっていた不安だった。 何年も前から、神殿の神官が魔物を退治するのに失敗するような事件が増えていた。人々は神官の経験の足りなさと言われ、それを信じているかのように振舞っていた。だが、巷の噂は尾ひれが付、神殿がその力を失いつつあるという恐ろしい事実が広まっていた。 人々は別に誰が呼びかけたわけでもないのに集まり始め、人数が集まると動き始めた。 |
|
|
とうとう、あの静かだった湖の魔物も神殿に逆らいはじめたのだ。このままではいつ、人々に危害が及ぶようになるかわからない。そうなるまえに、何とかしなければならない、というのが、人々の共通した思いだった。しかし、そうした人々の思いの中に、あの魔物が巣食っているのに誰も気づいていなかった。 あの魔物、暗く、冷たい闇の中を好む、最も魔物らしき魔物。 |
|
![]()
|
|
彼は人々をまるでよそ者か何かのように感じていた。彼らはこのガンダルフの人々なのだろうか。穏やかで争いなど好まない、人々のはずなのに。 「魔物だ、魔物を退治しろ!」 人々はそう叫ぶと、持っていた松明や石を湖に投げ込み始めた。 人々が持っているのは松明と石と枯れ枝だけで、他に魔物を退治するのに使う呪文など誰も知ってはいなかった。それなのに、それを少しも可笑しいと思わない。何かに扇動されているにしても、どこか変だった。 |
|
|
しだいに、湖が波立ち始めた。 「やめなさい。彼らは、操られているだけ。」 と、リーラは言った。 「操られている?誰にだ。」 と、彼は尋ねた。 「わからない?あの竜巻を起こした魔物によ。」 リーラには分かっていた。陰に陽に姿を見せず、蠢くものを。ガンダルフに来てから、常にそれを感じていた。 「どうやら、あいつはあなたが邪魔のようね。」 とリーラは、湖の魔物に言った。 |
|
|
|
「私は、あ奴などに興味がない。今まであったこともないし、これからも会うつもりがない。」 と、冷ややかに湖の魔物は言った。 「そんなこと、どうでもいいのよ。ただ、あなたの存在が気に食わないだけ。」 リーラは、人々を眺めていて、その中の誰かが何かを湖に投げ込んだのを見た。 それは、湖に投げ込まれると、水をドス黒く染めはじめた。 「毒だわ。」 「毒?」 |
|
|
彼は、驚いて繰り返した。ガンダルフに「毒」などというものがあるなど、聞いたことが無い。今まで彼が見ていた平和なガンダルフの世界が、ガラガラと音を立てて崩れていく。これは、一体何なのだ。何が起きているのか。 目の前に起きていることが、彼には信じがたかった。 神殿の神官たちがしている『魔物退治』ということは、確かに彼にとって受け入れにくいことだった。それを今まで実際に目にしたことはない。言葉では知っていても、それを現実に見るのは初めてだった。狂気のような人々の姿は、彼が予想していた以上にガンダルフの変化が大きいものであることを示していた。 |
|
|
|
彼の属していた太古のガンダルフの人々は、嘘・騙し・殺人などの犯罪など考えもしないような人々だった。外の世界へ出て知るようになったそうした悪徳は、その世界にまるで縁が無く、まことに争いのない平和な世界だったのだ。 リーラにはだいたい予想がついていた。あの、天空の城の中で何千何百万年も一人で過ごしてきた彼には、考えもつかない変化がすでにこの惑星には起きていたのだ。それを初めて見た彼の驚きはどんなであろうか。いや、初めてというよりも、認めたくなかったことかもしれない。 |
|
|
「あの毒、何とかできない?」 リーラはただ驚きで思考停止状態の天空の城の主に言った。 湖に黒い色が広がっていくにつれて、湖の魔物に変化が現れた。次第に、その皮膚が黒ずんでくる。 「まさか、あんな毒くらいで…。」 と、湖の魔物が呟いた。 リーラはすでにその毒の成分を解析していた。普通の毒でないことは初めからわかっていた。魔物には、人間に効くような毒など役に立たない。魔物に効く「毒」は、おそらくあの魔物が自ら作り出したものであろう。したがって、解毒剤などはない。 |
|
|
|
人間にはリーラ達の様子は見えない。 そのリーラと彼の目に、湖の魔物の弱っていく様子が明らかだった。 「私にはこの毒の解毒剤は作れない。あなたはどうなの?」 「何てことだ。毒など、ここにはなかったのに…。」 うわごとのように繰り返す彼の言葉を聞きながらリーラは待った。もし、それが本当のことならば、一つだけ解決する方法があるはずだった。 |
|
|
気がつくと、空は白み始めていた。暴徒と化した人々は、いつしか夢遊病者のように、家路をたどっている。まるで何もなかったように、人々は去っていった。 湖はどす黒い色で染まっていた。このままでは、この湖の水は死の水になってしまうだろう。そうなると、今度はこの湖を使っている川下の多くの人々が犠牲になってしまう。朝になれば、人々が目覚め、水を使い出す。早くしなければならない。 彼は黙って何かを見つめているようだった。宙にある何かを見つめている、リーラにはそう見えた。 |
|
|
|
その宙の一点がやがて白く固まり始めた。そして、それは白く輝く石になった。 彼はその石を手に取ると、湖の魔物に近づいた。湖の魔物は、もう意識のない状態で横たわっている。口の中で呪文のようなものを唱えると、彼はその石を湖の魔物の胸に近づけた。すると、その石は、スッと胸の中に入っていった。 いつしか太陽が山の端から昇っていた。湖の湖面がその光を受けて光る。 ゆっくりと、湖の魔物が目を開けた。 「私は、どうしたのだ?確か、毒が体に…。」 「もう、大丈夫だ。」 と彼は言った。 |
|
|
彼は認めざるをえなかった。すでにガンダルフは変化している。自分が気づかなかっただけなのだ。いや気づきたくなかったのかもしれない。彼の知っているガンダルフは争いなど考えそうもない平和な人々が住んでいたのだ。もうその人々はいない。とっくの昔にあの遠い宇宙の彼方へ去ってしまったのだ。彼一人を残して。 今彼は一人、ガンダルフに残りこれからの事を考えなければならない。また再びかつてのようなガンダルフを作ることができるのか、それとも新たな世界を作るのか。 |
|
|
|
湖は魔物の体がよくなるとともに、以前の澄んだ湖面を取り戻していた。 「間に合ったようね。」 リーラは初めて見た。あれは、ここに来る途中に立ち寄った宇宙で聞いたものに違いない。彼らは、「願いの叶う石」、と呼んでいた。白く光る石。昔むかしの伝説でしかない、という人々もいた。だが、点々とその伝説が残っていることは確かだった。それが、このガンダルフを起点としていることは、調査済みだった。この銀河ではこの辺りは、守護者が守っていると言われ恐れられていたが、その守護者が「願いの叶う石」を持っていると、いや作ることができるとも言われていた。今、それを目の前でリーラは見たのだ。 |
|
|
その「石」の伝説は、遠くリーラのいたグリトスのある銀河まで残っていた。ということは、このガンダルフの太古の人々はグリトスの属する銀河まで来たことを意味する。そんな太古の時代にそんな遠くまでやってくることができるとは、どのような人々だったのか、リーラは興味を持った。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|